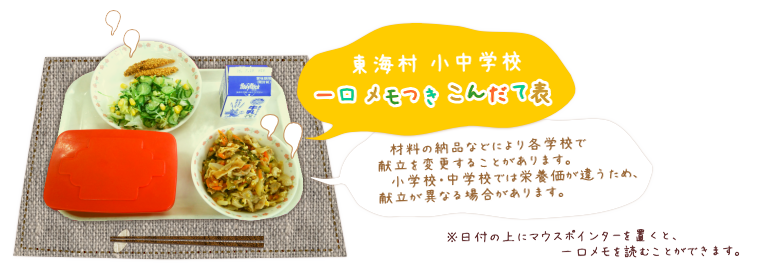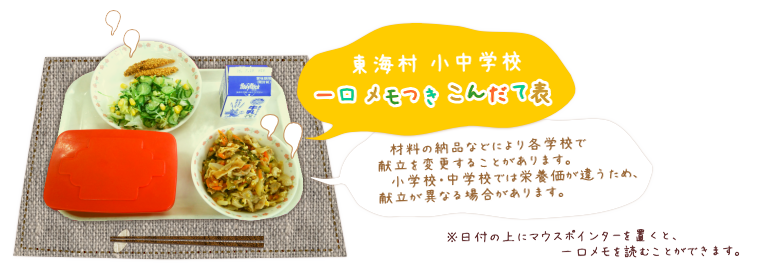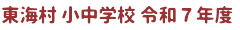  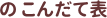 
- こちらに記載してあるメニューは、東海村共通献立です。学校により当日の献立(使われる食材やメニュー名など)が異なる場合があります。正しい献立は、各学校から配布される献立表をご覧ください。
- 食材名等記載された詳しいこんだて表は各学校のおたよりのページでご確認ください。
- 下のこんだてカレンダーにある旬の食材イラストの上にマウスポインターを置いてみてください。食品の豆知識がわかります!
|
| 日曜日 |
月曜日 |
火曜日 |
水曜日 |
木曜日 |
金曜日 |
土曜日 |
1
 2026年の恵方は「南南東」だそうです。恵方巻きはよく噛んで、美味しさをかみしめながらゆっくり楽しんで食べてくださいね! 2026年の恵方は「南南東」だそうです。恵方巻きはよく噛んで、美味しさをかみしめながらゆっくり楽しんで食べてくださいね! |
2 いちごといえば、赤色を思い浮かべる人が多いと思います。しかし、今では日本国内だけでも約300種類のいちごがあり、赤色だけではなく、白色、ピンク色、黒色などもあります。
茨城県は、全国でも有数のいちごの産地で、茨城県オリジナル品種「いばらキッス」や「ひたち姫」などがあります。
いちごは、風邪の予防をするビタミンCが豊富に含まれています。その他にもお腹の調子を良くする食物せんいや、虫歯予防に役立つキシリトールなども含まれています。
黒パン 牛乳 豆乳のクリームシチュー 海藻サラダ |
3 節分は、季節を分けるという意味があり、この日を境に冬から春になるとされています。節分に行う豆まきは、病気を起こす悪い気を追い払って、春を呼び込むという意味が込められています。また、歳の数より1つ多く豆を食べ、「1年を無事で健康に過ごせますように」と願っています。そして、いわしの頭を柊の小枝に刺して戸口に飾るのは、いわしの臭いと柊のとげが、鬼を追い払うためだと言われています。日本の伝統を大切にし、今年も元気に過ごしましょう。
米飯 牛乳 いわしの梅煮 カリカリ大豆サラダ 根菜のみそ汁 | 4 昔から若返りの薬として信じられ、縁起の良いものと神様にお供えした食べ物は、次のうちどれでしょう。(1)鶏肉、(2)うどん、(3)わかめ …答えは、(3)わかめです。わかめは、漢字で「若い芽」と書くように聞こえることから、若返りの薬として信じられていました。骨や歯を強くするカルシウムや、高血圧を予防するカリウムなどが豊富に含まれています。わかめは、汁物や和え物、サラダなど、様々な料理に使われています。
米飯 牛乳 ビビンバの具 わかめスープ | 5 東海村は、今年で70周年を迎えます。東海村の南側に広がる広大な水田地帯「真崎浦」を知っていますか?現在は水田ですが、昔は大きな湖でした。そこで人々はコイやフナをとったりレンコンを育てて暮らしていましたが、大雨のたびに水があふれてしまったため、湖の水を抜いて、田んぼにしました。普段、見慣れている風景も昔は全然違う風景だったと考えると面白いですね。
米飯 牛乳 肉じゃが ほうれん草のごま和え |
6 「からし」は何から作られるか知っていますか?「からし」は「からし菜」という野菜の種から作られます。ヨーロッパでは昔から塗り薬や湿布としても使われてきたスパイスです。日本では薬味や漬け物、和え物など、いろいろな日本料理に使われています。納豆にもからしが入っていますね。ツンとした香りで、少しピリッと辛いと思いますが、この辛みには食欲を増す効果があります。今日は和え物に使いました。からしの風味が野菜のおいしさを引き立てています。
米飯 牛乳 ハンバーグ からし和え 実だくさん汁 |
7
 はまぐりは4月から産卵期に入り、その直前は身も太く美味しくなります。ひなまつりに食べると「良縁」を招くとされ、お吸い物などによく使われます。国産のはまぐりは茨城県鹿島灘の漁獲量がもっとも多いそうです。 はまぐりは4月から産卵期に入り、その直前は身も太く美味しくなります。ひなまつりに食べると「良縁」を招くとされ、お吸い物などによく使われます。国産のはまぐりは茨城県鹿島灘の漁獲量がもっとも多いそうです。 |
8
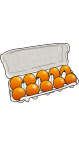 たまごはどうして卵型なのでしょうか?鳥は、樹の上の高い巣にたまごを産ります。まん丸の形だと、巣から落ちやすくなるため、転がっても元の位置に戻るようにこの形になったと言われています。 たまごはどうして卵型なのでしょうか?鳥は、樹の上の高い巣にたまごを産ります。まん丸の形だと、巣から落ちやすくなるため、転がっても元の位置に戻るようにこの形になったと言われています。 |
9 花豆はいんげんの仲間です。鮮やかな赤色や白い大きな花をたくさん咲かせるのが特徴で、それが名前の由来になっています。赤い花からは紫花豆、白い花からは白花豆がとれます。花豆の種が日本に伝わったのは、江戸時代の終わりころですが、花が大きくてきれいなため、当時は花を楽しむために栽培されていました。とても大粒で食べ応えがあることから、煮豆や甘納豆によく使われています。
牛乳 ソース焼きそば 白花豆コロッケ ブロッコリーのマヨサラダ いちごヨーグルト | 10 みなさん、ベーコンとハムの違いを知っていますか?ベーコンは、豚ばら肉を塩漬けしてから燻製して作ります。燻製しているので、香りや旨味、コクがあります。ハムは、豚もも肉やロース肉を塩漬けしてから茹でたり蒸したりして作ります。あっさりとした味わいでサンドイッチやサラダに使うと他の食材の味を引き立てます。今日は、バンサンスーにハムが入っています。味わっていただきましょう。
米飯 牛乳 豆腐の中華煮 バンサンスー | 11
 水菜は伝統ある京野菜です。水と土のみで作られていたので「水菜」と呼ばれます。京野菜を代表する青菜で、関東では「京菜」とも呼ばれています。 朝鮮半島で「タラ」は昔から「ミョンテ(明太)」と呼ばれ、卵が食べられてきました。この「ミョンテ(明太)」の卵ということで「明太子」と呼ばれていたのが今もそのまま用いられ「めんたいこ」になったそうです。 水菜は伝統ある京野菜です。水と土のみで作られていたので「水菜」と呼ばれます。京野菜を代表する青菜で、関東では「京菜」とも呼ばれています。 朝鮮半島で「タラ」は昔から「ミョンテ(明太)」と呼ばれ、卵が食べられてきました。この「ミョンテ(明太)」の卵ということで「明太子」と呼ばれていたのが今もそのまま用いられ「めんたいこ」になったそうです。
| 12 小学校6年生と中学校3年生を対象に給食総選挙を行いました。2月、3月の給食には、給食総選挙で上位に選ばれたメニューが登場します。今日は、主食・主菜部門で第2位に選ばれた「ココア揚げパン」と、副菜・汁物部門で第1位に選ばれた「ワンタンスープ」です。給食で使用しているワンタンは、小麦粉を薄く伸ばして作られており、具を包まずに皮だけを使用しています。つるんとした食感を楽しんで食べてください。
ココア揚げパン(胚芽パン) 牛乳 オニオンドレッシングサラダ ワンタンスープ |
13 暦の上では春ですが、まだまだ気温が低く、空気が乾燥する日が続きます。気温が低く乾燥する時期は、ウイルスが活動的になり、かぜやインフルエンザにかかりやすくなります。かぜをひかないようにするためには、栄養バランスの良い食事が欠かせません。特に、粘膜を強くするカロテンやビタミンA、抵抗力を高めるビタミンC、免疫細胞をつくるタンパク質を意識してとりましょう。今日の給食では、ビタミンAは、ほうれん草やにんじん、ビタミンCはじゃが芋やほうれん草から、タンパク質は牛乳や豚肉、ご飯からとることができます。
米飯 牛乳 鶏肉と厚揚げのうま煮 即席漬け
 |
14
 カレー南蛮の「南蛮」は実はネギのことです。江戸時代に来日した南蛮人がネギを好んで健康のために食していたからと言われています。 カレー南蛮の「南蛮」は実はネギのことです。江戸時代に来日した南蛮人がネギを好んで健康のために食していたからと言われています。
|
15
 カットした白菜を買ったら真ん中(芯のまわり)から食べると良いと言われています。一番甘みがあって、外葉の栄養がそれ以上芯にとられてしまうのも防いでくれるそうです。 カットした白菜を買ったら真ん中(芯のまわり)から食べると良いと言われています。一番甘みがあって、外葉の栄養がそれ以上芯にとられてしまうのも防いでくれるそうです。 |
16 ミネストローネは、イタリア語で「具だくさんのスープ」を意味し、イタリアの家庭で古くから親しまれている、野菜たっぷりのスープです。使われる食材は様々で、野菜といっしょにベーコンなどの肉類や豆、パスタや米などを加えて煮込みます。日本ではミネストローネというと、トマトベースの赤いスープという印象が強いかもしれませんが、イタリアではトマトが入らない、白いミネストローネもあります。野菜がたっぷり含まれているため、ビタミンや食物繊維などの栄養素を一度に摂ることができる健康的なスープです。
ミルクパン 牛乳 プレーンオムレツ 粉ふきいも ミネストローネ |
17 食物アレルギーは、好き嫌いとは違い、ある食べ物を食べるとアレルギー症状が出ることをいいます。食物アレルギーは、人によって原因になる食べ物や症状などが違います。今日の給食は、食物アレルギーをもつ児童・生徒の皆さんも一緒に給食が食べられるように、アレルギーの原因となる食品を使わない献立を作成しました。食物アレルギーについて考えながら、みんなで楽しく食べましょう。
米飯 豆乳ココア味 チキンカレー コーンサラダ
 |
18 焼売は、日本の定番中華メニューとして親しまれている料理です。蒸して作るのが一般的ですが、なぜ「焼」という文字が付いているのでしょうか。「焼売」という名称の由来にはいくつかありますが、ひとつは中国語の「焼」という字に惣菜を作る、調理するという意味があり、作った惣菜を街中で販売する意味で、「焼売」と名付けられたといわれます。また、かつての中国は伝染病を防ぐために、真っ黒になった麦を焼いていたそうです。その姿が焼売に似ていたことから「焼いた麦」と書いて「焼麦」と読み、それが「焼売」になったという説もあります。
みそラーメン 牛乳 ポークしゅうまい 寒天入りヘルシーサラダ
 |
19 今日の魚は「もうか」です。もうかは「もうかざめ」というサメの仲間で体長3メートルの大きな魚です。東北地方の宮城県で捕れるそうです。「さめ」と聞いてびっくりするかもしれませんが、実は昔から食べられてきた食材です。かまぼこ・はんぺんなどの材料として使われたりしています。今日はもうかを揚げて、甘酸っぱいタレで絡めたもうかの甘酢あんです。おいしくいただきましょう。
米飯 牛乳 もうかの甘酢あん おひたし ごまみそ汁
 |
20 毎月20日は「いばらき美味しおDay」、そして「とうかい減塩Da y」です。茨城県は、心臓の病気や脳の病気などの生活習慣病による死亡率が全国に比べて多 く、その原因の一つの食塩摂取量も、国が定める目標量を大幅に超えています。そこで、茨城県や東海村では、減塩の取り組みをしています。給食の豚汁は、給食室で毎朝かつお節からだしを取って、作っています。だしの香りで少ない食塩でも美味しく食べることができます。また、具だくさんに仕上げることで、食塩を多く含む汁の量を減らすことができるので、より減塩することができます。
米飯 牛乳 納豆 切り干し大根の炒め煮 豚汁
 |
21
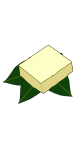 豆腐を作るときに出るしぼりカスの「おから」は、別名”卯の花(うのはな)”です。卯の花というのは白い花を咲かせるウツギの花のことです。白いおからをウツギの花にたとえて、卯の花と言われています。 豆腐を作るときに出るしぼりカスの「おから」は、別名”卯の花(うのはな)”です。卯の花というのは白い花を咲かせるウツギの花のことです。白いおからをウツギの花にたとえて、卯の花と言われています。 |
22
 2月はバレンタインデーがありますね。女性から男性にチョコレートを渡すのは、なんと日本独自の文化だそうです。アメリカでは男性が花束とカードを添えて愛を伝える日なのだとか。国によって違いがあって面白いですね。 2月はバレンタインデーがありますね。女性から男性にチョコレートを渡すのは、なんと日本独自の文化だそうです。アメリカでは男性が花束とカードを添えて愛を伝える日なのだとか。国によって違いがあって面白いですね。 |
23
 あさりは海水中の微生物を食べるので、海水をきれいにしてくれます。1匹のあさりで1時間0.6~1リットルの水をろ過することができ、20匹が10時間かければなんどドラム缶1本分(200リットル)をろ過できそうです。 あさりは海水中の微生物を食べるので、海水をきれいにしてくれます。1匹のあさりで1時間0.6~1リットルの水をろ過することができ、20匹が10時間かければなんどドラム缶1本分(200リットル)をろ過できそうです。 |
24 今日の回鍋肉には黒いキクラゲが入っています。さてキクラゲは、海の食材、山の食材どちらでしょう。正解は、山の食材です。キクラゲと聞くと「クラゲ」という名前から海の食材と思うかもしれません。しかし実は、山の食材できのこの仲間なのです。キクラゲは味にクセがなく、コリコリとした食感が特徴です。食感も楽しみながら食べてみてください。
米飯 牛乳 回鍋肉 中華あえ
 |
25 麩は、小麦粉のグルテンという成分を、水で練った生地から作られます。生地を蒸した生麩、油で揚げた油麩、乾燥させてから焼いた焼き麩といった種類があります。今日の青菜炒めには、刻んだ焼き麩が入っています。調理する前は、乾燥していてかたい焼き麩ですが、野菜と一緒に炒めると、野菜から出るうま味を吸って、ふっくらとやわらかくなります。シャキシャキとした野菜と焼き麩の食感の違いを楽しんでいただきましょう。
米飯 牛乳 鶏肉の唐揚げ 青菜炒め はるさめスープ |
26 ジャムは、果物を砂糖とレモン汁と一緒にじっくり煮て作ります。果物のペクチンという成分が、砂糖やレモンの酸っぱさと合わさることで、とろっとしたジャムになります。水を入れないので、果物の味を濃く味わうことができます。いちばん美味しい旬の時期に収穫した果物は、ジャムにすることで長く保存することが出来ます。今日の給食は、10月から12月が旬のりんごで作ったりんごジャムです。
コッペパン 牛乳 ポトフ ガーリックドレッシングサラダ りんごジャム
|
27 食事のマナーのひとつに、正しい食器の並べ方があります。食器を正しく並べられているか、確認してみましょう。ご飯は、食器を持つ回数がいちばん多いので、左の手前に置き、汁物は、こぼさないように取りやすい右の手前に置きます、主菜と副菜は、奥に置き、牛乳は、右奥に置きましょう。出来ていましたか?食器の並べ方は、食事のマナーのひとつです。明日からもマナーを守って給食をいただきましょう。
米飯 牛乳 さばのカレー焼き 昆布あえ 大根と油揚げのみそ汁 |
28
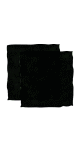 のりは海外でも食べられていますが、のりの成分を分解する酵素を体の中に持っているのは、世界中で日本人だけだそうです。 のりは海外でも食べられていますが、のりの成分を分解する酵素を体の中に持っているのは、世界中で日本人だけだそうです。 |
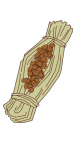 日本以外の国にも納豆のような食べ物があります。例えばインドネシアの「テンペ」ネパールやブータンには「キネマ」インドには「バーリュ」。使っている菌や形などは違いますが大豆を使ったおいしい発酵食品です。 日本以外の国にも納豆のような食べ物があります。例えばインドネシアの「テンペ」ネパールやブータンには「キネマ」インドには「バーリュ」。使っている菌や形などは違いますが大豆を使ったおいしい発酵食品です。 |
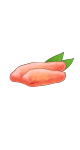 朝鮮半島で「タラ」は昔から「ミョンテ(明太)」と呼ばれ、卵が食べられてきました。この「ミョンテ(明太)」の卵ということで「明太子」と呼ばれていたのが今もそのまま用いられ「めんたいこ」になったそうです。 朝鮮半島で「タラ」は昔から「ミョンテ(明太)」と呼ばれ、卵が食べられてきました。この「ミョンテ(明太)」の卵ということで「明太子」と呼ばれていたのが今もそのまま用いられ「めんたいこ」になったそうです。
|
 ほろ苦い春の味、菜の花。つぼみが開いておらず、茎の切り口がみずみずしく軸の中心まで緑色のものが新鮮で美味しいものです。 ほろ苦い春の味、菜の花。つぼみが開いておらず、茎の切り口がみずみずしく軸の中心まで緑色のものが新鮮で美味しいものです。 |
 流通しているかきは、ほとんどが養殖ものです。天然の岩ガキは、獲れる量が限られているため、非常に高価です。「海のミルク」とよばれるほど、豊富な栄養を持ちます。 流通しているかきは、ほとんどが養殖ものです。天然の岩ガキは、獲れる量が限られているため、非常に高価です。「海のミルク」とよばれるほど、豊富な栄養を持ちます。 |
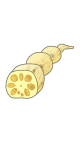 茨城県で全国の半分近くを生産しています。れんこんを保存するときは切り口が空気に触れると変色してしまうのでラップで切り口をピッタリと包んで保存するとよいそうです。 茨城県で全国の半分近くを生産しています。れんこんを保存するときは切り口が空気に触れると変色してしまうのでラップで切り口をピッタリと包んで保存するとよいそうです。 |
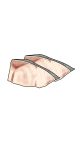 いなだ・はまちは同じ魚、どちらも「ぶり」。ぶりの40センチ程度の大きさのもので、関東では「いなだ」関東以外の一部地域では「はまち」と呼ばれています。しかし回転寿司などで見かける「はまち」はただの呼び方ではなく「養殖のぶり」を指しています。 いなだ・はまちは同じ魚、どちらも「ぶり」。ぶりの40センチ程度の大きさのもので、関東では「いなだ」関東以外の一部地域では「はまち」と呼ばれています。しかし回転寿司などで見かける「はまち」はただの呼び方ではなく「養殖のぶり」を指しています。 |
 「霜にあたると甘みを増す」といわれますが、ほうれん草自身が寒さから身を守るため、成分を充実させるからなのですね。旬のものは味がよいだけでなく、栄養もたっぷりというわけです。 「霜にあたると甘みを増す」といわれますが、ほうれん草自身が寒さから身を守るため、成分を充実させるからなのですね。旬のものは味がよいだけでなく、栄養もたっぷりというわけです。 |
 東海村の学校給食レシピのページはこちらからどうぞ! 東海村の学校給食レシピのページはこちらからどうぞ!
 は、おはしを使う給食の日です。 は、おはしを使う給食の日です。
- 東海村の学校給食では、東海村産の小松菜・なす・キャベツ・さつまいもなどを季節によって使用します。
- 米は東海村産「コシヒカリ」を100パーセント使用しています。
- 納品の都合等により、各学校で献立を変更することがあります。正しい献立は、各学校から配布される献立表をご覧ください。
- アレルギー等、気になるメニューがありましたら学校までおたずね下さい。
- 学校・保育所給食食材の放射性物質測定については、東海村のホームページをご覧下さい。
|